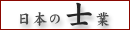07年05月25日
休職期間満了と雇用契約の終了
事案は、「Xは、Y会社において勤務中、過去に行われたデモに参加し、公務執行妨害罪及び凶器準備集合罪に当たる行為をした嫌疑をもって逮捕され、約6ヶ月勾留され欠勤を余儀なくされた。本件欠勤について、Yは、最初の40日間についてはXが保有していた有給休暇を振り替えて休暇扱いとし、次の1ヶ月間を「事故欠勤」として扱い、その満了時翌日には事故欠勤が引き続き30日以上に及ぶときは休職させることがあると定める就業規則に基づき、Xを休職に付した。さらに、30日後翌日には、事故欠勤休職の期間を30日と定め、かつ、休職期間満了時にはその従業員は退職するものとする旨定める就業規則の規定に基づき、その旨をXに通告した。これに対し、Xは、本件休職処分は無効で、自分には雇用契約上の地位があると主張したもの」である。
これは、石川島播磨重工業事件であるが、最高裁(最判S57,10,8)は次のように判示した。
1 原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
2 (原判決)
(1) Xの、通常解雇事由がある場合に限り「事故欠勤休職」処分ができると解さなければ「事故欠勤休職」 制度が解雇の制約を免れるために利用される虞があるとの主張に対し、「仮に本件「事故欠勤休職」制度が条件付解雇の性格を帯びるとしても、解雇の制限に関する労基法19条の規定と抵触するものでないことは明らかであるのみならず、労基法20条との関係においてこれを見ても、その期間内に限り復職を可能とする1ヶ月の解雇猶予期間を設定しているのであるから、同条所定の予告解雇よりも従業員にとって有利となる場合もあり得るのであって、これをもって同条に違反するものとすることができない。」とした。
(2) Xの、本件欠勤のごとく刑事事件によって逮捕勾留されたことによる欠勤は、他の自己都合による欠勤と区別して取り扱うべきとの主張に対し、「本件「事故欠勤休職」制度は、就労意思の有無はともかく、一定期間にわたる労務の不提供それ自体をもって休職事由とするものであり、この点においては他の自己都合による欠勤と何ら区別すべき点がない。」とした。
(3) 「事故欠勤休職」処分は、その実質において解雇猶予処分に当たるとみられなくはないが、当該就業規則の規定は通常解雇に関する就業規則の規定とは別に、独立した雇用契約終了事由としてこれを規定したものであることが、その規定の文理に照らして明らかであるし、通常解雇とは別の雇用契約終了事由を就業規則上設定することが許されないとする理はない。
(4) 以上のとおり、本件「事故欠勤処分」の無効を前提とするXの本訴請求は、既に他の争点について判断するまでもなく理由がないから、これを失当として棄却する。
合理的な就業規則は、使用者にとっても、労働者にとっても、紛争解決の基準となります。10人以上の労働者がいる場合に就業規則の作成が義務付けられていますが、10人未満でも就業規則を作成しておくと、未然に労働紛争を回避することができます。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
これは、石川島播磨重工業事件であるが、最高裁(最判S57,10,8)は次のように判示した。
1 原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
2 (原判決)
(1) Xの、通常解雇事由がある場合に限り「事故欠勤休職」処分ができると解さなければ「事故欠勤休職」 制度が解雇の制約を免れるために利用される虞があるとの主張に対し、「仮に本件「事故欠勤休職」制度が条件付解雇の性格を帯びるとしても、解雇の制限に関する労基法19条の規定と抵触するものでないことは明らかであるのみならず、労基法20条との関係においてこれを見ても、その期間内に限り復職を可能とする1ヶ月の解雇猶予期間を設定しているのであるから、同条所定の予告解雇よりも従業員にとって有利となる場合もあり得るのであって、これをもって同条に違反するものとすることができない。」とした。
(2) Xの、本件欠勤のごとく刑事事件によって逮捕勾留されたことによる欠勤は、他の自己都合による欠勤と区別して取り扱うべきとの主張に対し、「本件「事故欠勤休職」制度は、就労意思の有無はともかく、一定期間にわたる労務の不提供それ自体をもって休職事由とするものであり、この点においては他の自己都合による欠勤と何ら区別すべき点がない。」とした。
(3) 「事故欠勤休職」処分は、その実質において解雇猶予処分に当たるとみられなくはないが、当該就業規則の規定は通常解雇に関する就業規則の規定とは別に、独立した雇用契約終了事由としてこれを規定したものであることが、その規定の文理に照らして明らかであるし、通常解雇とは別の雇用契約終了事由を就業規則上設定することが許されないとする理はない。
(4) 以上のとおり、本件「事故欠勤処分」の無効を前提とするXの本訴請求は、既に他の争点について判断するまでもなく理由がないから、これを失当として棄却する。
合理的な就業規則は、使用者にとっても、労働者にとっても、紛争解決の基準となります。10人以上の労働者がいる場合に就業規則の作成が義務付けられていますが、10人未満でも就業規則を作成しておくと、未然に労働紛争を回避することができます。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年05月24日
転籍と従業員の地位
事案は、「Xは、Y会社の横浜工場の従業員であったが、Y会社が系列会社であるZ会社に転属させる意向をXに対して伝えたところ、Xはこれを了承した。しかし、Z会社はXに対して雇うことができない旨の通知をし、また、Y会社も、Xを退職したものとして取り扱い、Xが横浜工場の従業員であることを否定しているというもの」である。
これは、日立製作所横浜工場事件であるが、最高裁(最判S48,4,12)は次のように判示した。
1 原審が、「労働者であるXの承諾があってはじめて転属の効力が生ずる」ものとした判断は、相当として是認することができる。
2 原判決の要旨を述べると、「本件転属がY会社のXとの間の労働契約上の地位の譲渡であり、Y会社とZ会社との間の本件転属に関する合意が成立した以上、Xがこれを承諾すれば、Y会社のXとの間の労働契約上の地位は直ちにZ会社に移転する」から、「XはY会社の従業員たる地位を失うと同時に、当然Z会社の従業員たる地位を取得するものというべく、その間に改めてZ会社との間に労働契約を結ぶ余地のないことは明白である。」ということになる。
3 そして、Z会社で支障なく就労できることが本件転属承諾の要素となっていたことは明白であるところ、XはZ会社で就労させてもらえるものと信じて本件転属を承諾したのに、当時すでにZ会社ではその就労拒否を決定していたのであるから、「右承諾は要素に錯誤があり、無効」といわざるを得ない。
Xの、「本件転属はZ会社がXを雇うことを条件とするY会社とXとの間の労働契約の合意解約」である旨の主張を退けて、「Xの承諾があってはじめて転属の効力が生じるが、その承諾は要素に錯誤があるから無効」として、転属の効力は生じないとしたものです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
これは、日立製作所横浜工場事件であるが、最高裁(最判S48,4,12)は次のように判示した。
1 原審が、「労働者であるXの承諾があってはじめて転属の効力が生ずる」ものとした判断は、相当として是認することができる。
2 原判決の要旨を述べると、「本件転属がY会社のXとの間の労働契約上の地位の譲渡であり、Y会社とZ会社との間の本件転属に関する合意が成立した以上、Xがこれを承諾すれば、Y会社のXとの間の労働契約上の地位は直ちにZ会社に移転する」から、「XはY会社の従業員たる地位を失うと同時に、当然Z会社の従業員たる地位を取得するものというべく、その間に改めてZ会社との間に労働契約を結ぶ余地のないことは明白である。」ということになる。
3 そして、Z会社で支障なく就労できることが本件転属承諾の要素となっていたことは明白であるところ、XはZ会社で就労させてもらえるものと信じて本件転属を承諾したのに、当時すでにZ会社ではその就労拒否を決定していたのであるから、「右承諾は要素に錯誤があり、無効」といわざるを得ない。
Xの、「本件転属はZ会社がXを雇うことを条件とするY会社とXとの間の労働契約の合意解約」である旨の主張を退けて、「Xの承諾があってはじめて転属の効力が生じるが、その承諾は要素に錯誤があるから無効」として、転属の効力は生じないとしたものです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年05月23日
出向命令と権利の濫用
事案は、「X らは、Y会社に入社し、製鉄所内の構内鉄道輸送業務に従事していた。Yは業界全体の不況に際し、業務委託と出向を内容とする再構築計画を策定し、各対象者に承諾を求めるという方法で出向者を決定した。しかし、X らは同意しなかったが、Y は組合の了解を得た上で、X らに出向を命令したもの」である。
これは、新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件であるが、最高裁(最判H15,4,18)は次のように判示した。
1 (1)本件各出向命令は、委託される業務に従事していたXらにいわゆる「在籍出向」を命ずるものであること、(2)Yの就業規則には、「会社は従業員に対し、業務上の必要によって社外勤務させることがある。」という規定があること、(3)労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり、労働協約である社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当て、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること、という事情の下においては、YはXらに対し、「その個別的合意なしに」、Yの従業員としての地位を維持しながら出向先の会社においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することができるというべきである。
2 (1)鉄道輸送部門の一定の業務を委託することとした経営判断の合理性、(2)委託される業務に従事していたYの従業員につき出向措置を講ずる必要性、(3)出向措置の対象となる者の人選基準の合理性及び具体的人選についての不当性をうかがわせる事情の欠如、(4)本件各出向命令によって、Xらの労務提供先は変わるものの、その従事する業務内容や勤務場所には何らの変更はなく、上記社外勤務協定の規定等を勘案すれば、Xらがその生活関係、労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえないこと、(5)本件各出向命令の発令手続に不相当な点があるともいえないこと、等の事情に鑑みれば、本件各出向命令が権利の濫用に当たるということはできない。
として、原審の判断を正当として是認しました。
やはり出向に関しても、労働協約や就業規則にチャンと規定しておくべきなのです。勿論、「合理的内容」を有するものでなければなりません。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
これは、新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件であるが、最高裁(最判H15,4,18)は次のように判示した。
1 (1)本件各出向命令は、委託される業務に従事していたXらにいわゆる「在籍出向」を命ずるものであること、(2)Yの就業規則には、「会社は従業員に対し、業務上の必要によって社外勤務させることがある。」という規定があること、(3)労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり、労働協約である社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当て、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること、という事情の下においては、YはXらに対し、「その個別的合意なしに」、Yの従業員としての地位を維持しながら出向先の会社においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することができるというべきである。
2 (1)鉄道輸送部門の一定の業務を委託することとした経営判断の合理性、(2)委託される業務に従事していたYの従業員につき出向措置を講ずる必要性、(3)出向措置の対象となる者の人選基準の合理性及び具体的人選についての不当性をうかがわせる事情の欠如、(4)本件各出向命令によって、Xらの労務提供先は変わるものの、その従事する業務内容や勤務場所には何らの変更はなく、上記社外勤務協定の規定等を勘案すれば、Xらがその生活関係、労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえないこと、(5)本件各出向命令の発令手続に不相当な点があるともいえないこと、等の事情に鑑みれば、本件各出向命令が権利の濫用に当たるということはできない。
として、原審の判断を正当として是認しました。
やはり出向に関しても、労働協約や就業規則にチャンと規定しておくべきなのです。勿論、「合理的内容」を有するものでなければなりません。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年05月22日
配置転換命令権と権利の濫用
事案は、「二度にわたり転勤の内示があった者が、母が高齢(71歳)であり、保母をしている妻も仕事を辞めることが難しく、子供も幼少である(2歳)という家庭の事情により転居を伴う転勤には応じられないとして、これを拒否したところ、二度目には本人の同意がえられないままに転勤が発令された。しかし、これに応じなかったところ、就業規則所定の懲戒事由に該当するとして懲戒解雇されたもの」である。
これは、東亜ペイント事件であるが、最高裁(最判S61,7,14)は次のように判示した。
1 会社の労働協約及び就業規則には、業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、現に従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており、・・・・・・・・、両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという事情の下においては、「会社は個別的同意なしに勤務場所を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有する」ものというべきである。
2 転勤命令権を濫用することは許されないが、「当該転勤命令について業務上の必要性が存しない場合、または業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではない」というべきである。
3 そして、業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務能率の増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。
4 本件転勤命令については、業務上の必要性が優に存在し、本件転勤が与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものであるので、本件転勤命令は権利の濫用には当たらない。
通常、会社は転勤命令を出すことができるが、業務上の必要性がない場合や他の不当な目的でなされるとか、転勤により通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合などには、権利の濫用になり転勤命令は認められないということです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
これは、東亜ペイント事件であるが、最高裁(最判S61,7,14)は次のように判示した。
1 会社の労働協約及び就業規則には、業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、現に従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており、・・・・・・・・、両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという事情の下においては、「会社は個別的同意なしに勤務場所を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有する」ものというべきである。
2 転勤命令権を濫用することは許されないが、「当該転勤命令について業務上の必要性が存しない場合、または業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではない」というべきである。
3 そして、業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務能率の増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。
4 本件転勤命令については、業務上の必要性が優に存在し、本件転勤が与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものであるので、本件転勤命令は権利の濫用には当たらない。
通常、会社は転勤命令を出すことができるが、業務上の必要性がない場合や他の不当な目的でなされるとか、転勤により通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合などには、権利の濫用になり転勤命令は認められないということです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年05月21日
就業規則が効力を生じるためには周知が必要か
事案は、「旧就業規則を変更した新就業規則を実施した後に、旧就業規則時代の言動に対して、会社は新就業規則の懲戒解雇規定を適用して懲戒解雇にしたが、旧就業規則は事業場に備え付けられていなかったというもの」である。
これは、フジ興産事件であるが、最高裁(最判H15,10,10は、次のように判示した。
1 旧就業規則時代の言動については、旧就業規則における懲戒解雇事由が存するか否かについて検討すべきである(原審と同様)。
2 原審は、「旧就業規則は、労働者代表の同意を得た上で労働基準監督署長に届出ていたという事実が認められる以上、事業場に備え付けられていなかったとしても、労働者に効力を有しないと解することはできない。」としたのに対し、
最高裁は、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと要する。」 そして、「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する」ものというべきであるとして、原判決を破棄し、原審に差し戻した。
法律も国会で成立しただけでは効力を生じません。効力を生じさせようと思えば、「公布」が必要なのです。これと同様に、就業規則も労働者に「周知」させないと法的拘束力が生じないのです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
ページ移動
前へ
1,2, ... ,18,19,20,21
次へ
Page 19 of 21
これは、フジ興産事件であるが、最高裁(最判H15,10,10は、次のように判示した。
1 旧就業規則時代の言動については、旧就業規則における懲戒解雇事由が存するか否かについて検討すべきである(原審と同様)。
2 原審は、「旧就業規則は、労働者代表の同意を得た上で労働基準監督署長に届出ていたという事実が認められる以上、事業場に備え付けられていなかったとしても、労働者に効力を有しないと解することはできない。」としたのに対し、
最高裁は、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと要する。」 そして、「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する」ものというべきであるとして、原判決を破棄し、原審に差し戻した。
法律も国会で成立しただけでは効力を生じません。効力を生じさせようと思えば、「公布」が必要なのです。これと同様に、就業規則も労働者に「周知」させないと法的拘束力が生じないのです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。