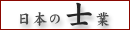07年07月25日
木製建具・・建具屋さんの腕の見せ所
外部にいわゆる木製製作建具を使うということは結構勇気のいることだと思いました。
狂う、腐る、高価、という3Kが揃って現在では新築住宅のほとんどに既成のサッシが使われています。
それでも立派な古民家には情緒漂う木製建具が使われていて目を引きます。
それで我々設計プロジェクトは思い切ってこの家には北側の一部を除いてすべて
木製建具にすることにしました。
地元の山田木工さんという親子二代で仕事をされている会社が担当して
くださったのですが、「木は生きている」ということを造る側も私たちも施主側も
身に沁みて実感、理解したと思います。
当然スムーズな開閉を期待していたのですが、ガラス戸、網戸、までは何とか
よいものの最後の雨戸がなかなか閉められず、何度も何度も経験して
1年後やっと慣れたという状態でした。
冬場に造ったので開け閉めはきつく、ずいぶん苦情が出ましたが、
夏場になれば乾燥し、木が縮むので開閉はずっと楽になるということで
がんばりました。おかげで一番大きな雨戸もなんとか操れるようになりました。
ベランダも冬場など誰も訪れない時は手摺の内側に雨戸を繰って防犯を徹底します。
狂う、腐る、高価、という3Kが揃って現在では新築住宅のほとんどに既成のサッシが使われています。
それでも立派な古民家には情緒漂う木製建具が使われていて目を引きます。
それで我々設計プロジェクトは思い切ってこの家には北側の一部を除いてすべて
木製建具にすることにしました。
地元の山田木工さんという親子二代で仕事をされている会社が担当して
くださったのですが、「木は生きている」ということを造る側も私たちも施主側も
身に沁みて実感、理解したと思います。
当然スムーズな開閉を期待していたのですが、ガラス戸、網戸、までは何とか
よいものの最後の雨戸がなかなか閉められず、何度も何度も経験して
1年後やっと慣れたという状態でした。
冬場に造ったので開け閉めはきつく、ずいぶん苦情が出ましたが、
夏場になれば乾燥し、木が縮むので開閉はずっと楽になるということで
がんばりました。おかげで一番大きな雨戸もなんとか操れるようになりました。
ベランダも冬場など誰も訪れない時は手摺の内側に雨戸を繰って防犯を徹底します。
07年07月23日
緊張する
基準法が改正されて初めての確認申請を明日提出することに。
軽井沢町なので景観育成に関して結構厳しい制約があったりします。
提出先である地方事務所へ不安な点を確認しようと思ったのですが、
えっ!ほっ本当かいな?チョットだけ安心・・・
 しかしこんな言葉に騙されずに、規則やら様式やら、今まで当たり前と思って
しかしこんな言葉に騙されずに、規則やら様式やら、今まで当たり前と思って
やっていたことをもう1度厳密に再チェックし、万全を
きして書類をまとめたのです。
が、なんとも不安な気持ちはなくなりません。
なんか忘れているのではないか?
今までの3倍は時間をかけて書類を作り、それでも提出して確認済証が
交付されるまでは、何週間?もこの不安な気持ちでいるのでしょうか?
軽井沢町なので景観育成に関して結構厳しい制約があったりします。
提出先である地方事務所へ不安な点を確認しようと思ったのですが、
「今まで通りでいいですよ」
というお返事が・・(^_^;)
というお返事が・・(^_^;)
えっ!ほっ本当かいな?チョットだけ安心・・・

やっていたことをもう1度厳密に再チェックし、万全を
きして書類をまとめたのです。
が、なんとも不安な気持ちはなくなりません。
なんか忘れているのではないか?
今までの3倍は時間をかけて書類を作り、それでも提出して確認済証が
交付されるまでは、何週間?もこの不安な気持ちでいるのでしょうか?
07年07月10日
”丸窓”って和みますね
こちらも「らいてうの家」に設けた丸窓です。
らいてうが生前住んでいた家の書斎に丸窓があって、
情緒漂う雰囲気を愛していたそうです。
らいてうが生前住んでいた家の書斎に丸窓があって、
情緒漂う雰囲気を愛していたそうです。
そこで会からの設計条件の筆頭に「和室に丸窓」が挙げられたのです。

うまくいきました。
文章で説明しても良く分からないと思いますので、まあとにかく
実際に来て見てくださいな( ^ -^)
PR・・・夏だからこそ羽根布団はいかが?
07年07月08日
ステンドグラス・・らいてうの家
ステンドグラスって教会の窓に当然のように使われて違和感もなく、
一番似合っていると思っていましたが、長野県あずまや高原に
建つ平塚らいてう記念山荘の展示ホール吹き抜けには山崎一彦さん
制作の「森と風のシンフォニー」という題のステキな作品があります。
山荘なのに違和感がなくかえってらいてうの家にふさわしく堂々と
愛着のあるデザインに思いました。

一番似合っていると思っていましたが、長野県あずまや高原に
建つ平塚らいてう記念山荘の展示ホール吹き抜けには山崎一彦さん
制作の「森と風のシンフォニー」という題のステキな作品があります。
山荘なのに違和感がなくかえってらいてうの家にふさわしく堂々と
愛着のあるデザインに思いました。

この夏遊びに来て見ませんか?
07年07月07日
若者に混じって楽しかったこと・・
少し前の話・・
建築士会の関東ブロック大会で神奈川大学へ行く機会がありました。
私たちは「平塚らいてう記念山荘」を地元の女性建築士9人が協同で設計監理した
ことが評価されて関ブロ大会へ出場することに。
神奈川大学のキャンパスで多くの学生に会い、学食で安くておいしい
カツカレーを食べ若返った気分で楽しみました。
メイン会場でのこと・・
ふと、正面のタイトルを見ると「〜青年建築士〜」とあるではないですか。
そうだったんだ・・これは青年建築士の大会だったんだ。
そういえば実行委員長もかなりお若く美しい女性でしたしスタッフもみな若い、
将来建築界をしょって立つ印象の方々ばかりでした。
50代になるとチョット自尊心が・・
もう若者の時代なのか・・
少しそんな風に弱気になったのでした。

11月までOPENしています。
よかったら高原へ遊びに来てくださいね( ^ -^)
NPO法人「平塚らいてうの会」
ページ移動
前へ
1,2,3,4,5, ... ,8,9
次へ
Page 4 of 9
建築士会の関東ブロック大会で神奈川大学へ行く機会がありました。
私たちは「平塚らいてう記念山荘」を地元の女性建築士9人が協同で設計監理した
ことが評価されて関ブロ大会へ出場することに。
神奈川大学のキャンパスで多くの学生に会い、学食で安くておいしい
カツカレーを食べ若返った気分で楽しみました。
メイン会場でのこと・・
ふと、正面のタイトルを見ると「〜青年建築士〜」とあるではないですか。
そうだったんだ・・これは青年建築士の大会だったんだ。
そういえば実行委員長もかなりお若く美しい女性でしたしスタッフもみな若い、
将来建築界をしょって立つ印象の方々ばかりでした。
50代になるとチョット自尊心が・・
もう若者の時代なのか・・
少しそんな風に弱気になったのでした。

11月までOPENしています。
よかったら高原へ遊びに来てくださいね( ^ -^)
NPO法人「平塚らいてうの会」